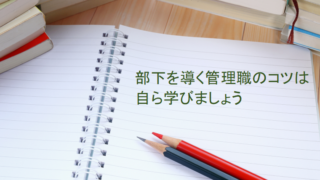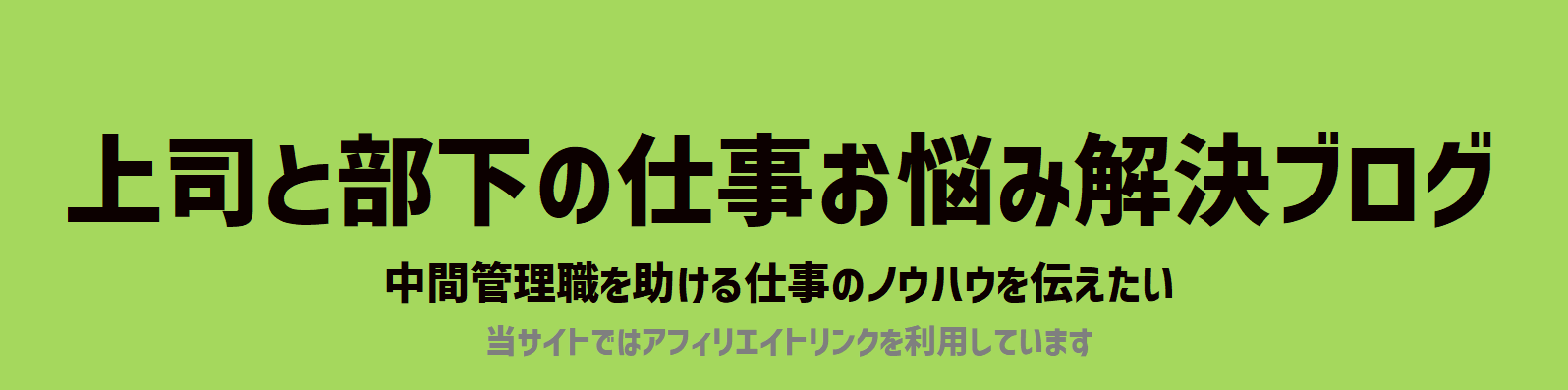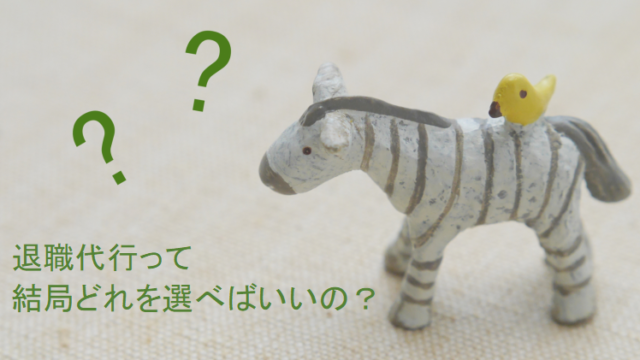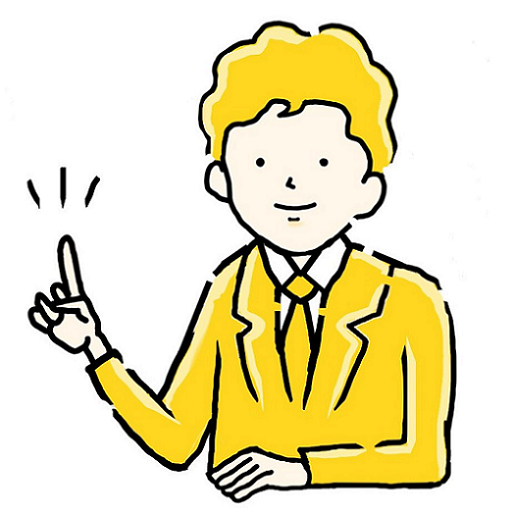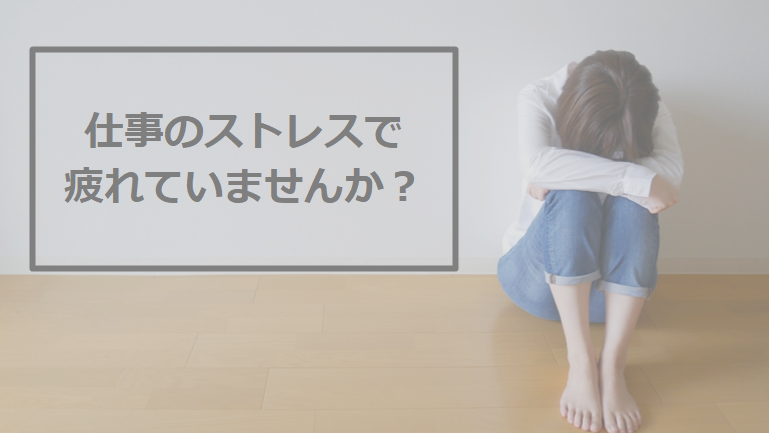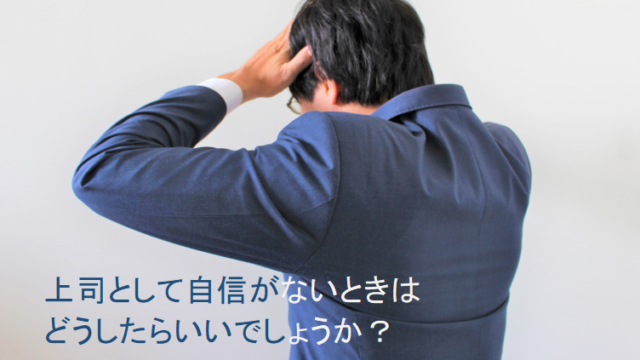「部下への指示が上手く伝わらない」という悩みは、多くの上司が抱えがちです。
出した指示と違う動きをとられたり、指示した仕事が期限までに間に合わなくて困ったことはないでしょうか。
「なぜ自分のイメージどおりに仕事をしてくれないのか」と悩み、部下の理解力の無さにイライラするかもしれません。
しかし、部下へ指示が伝わらないのは、上司のあなたに問題があると考えるべきです。
上司と部下ではスキルや経験、視野が違います。
その違いを配慮せずに指示をだしてしまうと、なかなか上手く伝わりません。
逆に、部下へ指示を出すときの注意点や、指示を上手く伝えるコツを把握すれば、部下への指示だしはスムーズにいくものです。
今回は、指示が伝わらない部下にもきちんと伝わる方法をまとめました。
ビジネスを進める上で、部下へ効果的に指示を出す力はリーダーにとって必須の能力です。
ちなみに、この記事では、「悪意はないが、未熟なために指示が伝わらない」という部下を想定しています。
未熟ではないはずなのに、あえて指示を聞いていないと感じる場合には、こちらの記事が参考になります。

目次
部下に指示が伝わらない3つの理由
まずは、なぜ部下に指示が伝わらないかという点について知ることが大切です。
「部下の理解力が無いから」という一言で片付けてしまっては、いつまで経っても部下への指示が上手くいきません。
これには大きく分けて3つの理由があります。
仕事の意義が伝わっていない
締め切りが近いはずなのに動きが遅い、仕事の出来がどうも雑・・という場合は、部下にその仕事の意義が十分に伝わっていないことが考えられます。
人間はロボットではないので、モチベーションによって仕事のスピードやクオリティが大きく変わるものです。
そして、人は自分の仕事に意義を感じているときにモチベーションが高まります。
その仕事が何のために必要なのか、なぜその部下にやってもらいたいのか、という点を詳しく伝えることが大切です。
部下に仕事の価値を感じさせることでやる気があがり、取り組みの速さやクオリティが上がります。
上司との信頼関係が無い
信頼している相手からの指示を受ける場合と、そうでない相手から言われる場合と、あなたはどちらの場合により本気で仕事に取り組めるでしょうか。
もちろん相手との信頼度合いに関係なく、きっちり仕事をしなければなりません。
しかし現実はそうではなく、部下の考え方が幼ければ幼いほど、「あの人は信頼できないから仕事が頑張れない」という意識になってしまいます。
そのような甘い考えをたたきなおすことも上司としては必要ですが、まずは部下と良好な信頼関係を築きましょう。
こちらの記事が参考になります。

上司の指示の出し方が下手
これは単純な話ですが、上司側がこのことを意識するのは重要なことです。
あなたの部下が、指示された内容を期待通りにこなせないのは、本当に部下の問題なのでしょうか。
スポーツ選手でもコーチが変わることで、成果を出すことができるように変わることがあります。
仕事でも同じことが言えます。指示通りに仕事ができるかどうかは部下の能力だけで決まりません。
部下に指示が伝わらないのは、上司であるあなたの指示の出し方に問題がある可能性があることを、認識しなければいけません。
下手な指示の出し方3パターン
部下に指示が伝わらない理由の一つとして、上司側の指示の出し方に問題がある可能性をご紹介しました。
では、具体的に「下手な指示の出し方」とはどういうものでしょうか。
パターンは様々ありますが、代表的なものを3つご紹介します。
指示の出し方があいまい
例えば、あなたが部下に、
「明日のプレゼンに使用する営業成績の報告資料、なるべく早く準備しておいて」
という指示を出したとします。
この指示にはあいまいな点がいくつもあります。
- 営業成績はいつからいつの期間の集計なのか
- 営業成績のうち、どのような項目の資料を作るのか
- 出力形式は紙なのか、パワーポイントなどのファイルなのか
- 「なるべく早く」とは今日の終業時までなのか、明日の午前中なのか
このようなあいまいさがいくつもあると、「部下が指示通り動かない」などの問題が生じます。
「分からないことがあるなら聞けばいいんだ」という上司もいますが、そういう上司に限って、実際に聞いたら「それくらい自分で考えろ」と答えるものです。
実際は、この例ほどあいまいな言い方をすることは少ないと思いますが、油断すると指示の一部があいまいな表現になってしまうものです。
そうなると、指示する上司と指示を受ける部下の間で、イメージのズレが生まれてしまうので注意しましょう。
思いつくままに伝えるため、部下が指示内容を整理できない
思いついたらその場で部下に仕事を指示したり、一度にたくさんの指示を出してしまうと、部下に上手く伝わらなくなります。
相手が理解できていないうちに次の指示の話をしたり、指示内容のポイントを把握できないまま話が終わったりすると、指示内容を上手く把握できません。
相手が理解できるペースで話さなければ結局は伝わらず、あとからもう一回指示しなおすなどの手間が生まれてしまいます。
優先順位がない
ある程度仕事に慣れていくと、複数の仕事を同時に行うことが多くなります。
そのときに、部下が仕事の優先順位を間違えてしまい、上司が最優先でやって欲しいことを差し置いて別の仕事に精を出している・・ということもよくあります。
部下の仕事の優先順位は、上司がつける必要があります。
上司がそれを怠ってしまうと部下が独自に優先順位をつけてしまい、優先的にやって欲しい仕事が後回しにされるという結果となります。
上司の指示の出し方が下手なパターンとしては、以上のような傾向があります。
そして、これらすべてに共通するのは、「言わなくても分かるだろう」という精神です。
- 多少あいまいに言っても分かってくれるだろう
- 思いつくままに指示を出しても理解できるだろう
- 自分で正しく優先順位をつけられるだろう
という上司側の思い込みが、あとから「なんで指示が伝わっていないんだ・・」という事態を生みます。
このような思い込みは、「部下への甘え」だと認識したほうが良いでしょう。
丁寧に指示を出す7つのコツ

このように、下手な指示の出し方というのがある一方、上手な指示の出し方もあります。
これから紹介する指示の出し方のコツを実践すれば、部下に指示が伝わらないと悩むことは少なくなるはずです。
仕事の意義を伝える
部下に指示を出すときには、なぜその仕事をする必要があるのかということもあわせて伝えましょう。
上のほうでも触れていますが、人はその仕事の意味や意義を理解することでモチベーションがあがります。
また、「その仕事に取り組むことで、部下自身がどのように成長するのか」ということもあわせて伝えられると、よりやる気があがります。
上司からすると、このような意義や意味を伝えるのは面倒くさく感じるかもしれません。
実際、仕事のやり方さえ教えれば、意義を伝えなくてもその仕事はこなせるものです。
しかし、やる気を上げれば仕事の質が上がるだけでなく、退職防止にもつながります。このひと手間を惜しまないようにしましょう。
伝え方を工夫する
思いつくままに部下へ指示するのではなく、部下が一つ一つの指示を理解し、消化しやすいように伝えるという工夫が重要です。
思いついたときに都度指示を出す方法は、部下の中で一日のスケジュールが狂ってしまうことになり、ヌケやモレが発生します。
そこで、毎日決まった時間にMTGを行い、そのときにまとめて指示を出せば部下もスケジューリングが落ちついてできます。
また、最初からすべてのステップについて説明するのではなく、途中までの作業指示を出し、それができたら次のステップについて指示を出すという方法をとれば、部下も一つ一つ確実に作業をこなせます。
優先順位を伝える
複数の仕事の指示を出すときには、どちらを優先するべきかを必ず伝えましょう。
これを間違えてしまうと、急いでやって欲しいことを後回しにされるということが起こります。
そして、ただ一つ一つの優先順位を指定するのではなく、部下が自分で優先順位をつけられるような考え方(お客様に直接関わる業務を優先する、資料作成は後回しにしてもいい、など)を常日頃から伝えることが重要です。
優先順位のつけ方が部下に浸透すると、自分で優先順位を判断できるようになり、いちいち指示する必要がなくなります。
具体的に伝える・イメージを共有する
指示の中にあいまいな言葉があると、上司と部下の間で認識の違いが生まれ、「イメージと違う!」と後からイライラすることになります。
「いつまでに」「なにを」「どのように」という点について具体的な言葉で表現し、イメージが違うことにならないように伝えましょう。
一番いいのは、出来上がりのサンプルや画像を見せることです。
言葉だけだと、想像するものが人によってズレることがありますが、画像で見ることで鮮明にイメージができるため、ズレが少なくなります。
サンプルの資料を見せるだとか、はじめは一緒にやってみせるなどを行い、イメージが共有できるようにしましょう。
つまづきやすいポイントを前もって伝えておく
その仕事のなかで、つまづきやすいところをあらかじめ伝えることで、部下がそこに注意し、上手に対処できるようになります。
また、部下としても、あらかじめそういうポイントを把握しておけば、その仕事への不安を少なくすることができます。
質問があるかどうか聞く
部下があなたからの指示をきちんと理解するためには、話を聞いて分からないところを質問させる必要があります。
質問ができないままだと、分からない点が解消させず、あとから認識の違いを生むことになります。
また、話を最初から最後まで一方的に話続けるのではなく、何度か途中で区切りながら質問をさせることで、相手の集中力も続きやすくなります。
復唱させる
これは指示を出し終わったら、本当に理解したかどうかを確認するために一番手っ取り早い方法です。
本当に分かっていれば、その指示がどういう内容なのかを、自分の言葉として口に出せます。
また、部下自身から「この話はこのようなことですね?」と確認してくることもあるでしょう。
そういう確認をしてくるというのは、指示の内容をある程度理解している証拠です。
部下から確認をしてこない場合は、ひととおり指示したあとに、「内容はわかった?指示の内容を復唱してごらん?」と問いかけてみることで相手に復唱してもらましょう。
適切な指示の出し方の例
以上のようなポイントを押さえて部下に指示を出すことで、部下に指示内容がきちんと伝わります。
注意すべきポイントが多くあり大変ですが、例えば以下のような形で指示を出してみると良いでしょう。
例えば、営業成績の資料作成を指示する場合を考えてみます。
「来週の会議に使う営業資料の作成をお願いしたいんだけどいいかな。」
「来週の会議では、営業課ごとに月別の営業成績を発表するんだけど、前月比の営業成績や、年間目標の進捗率を報告するために使うんだ。」
(なぜその仕事が必要なのか)
「この資料は営業部の課長以上のメンバーに配られ、当日はこの資料をもとに報告したり指摘を受けるので、私も数字のチェックをしたいから、会議の2日には私の手元にあるようにして欲しい」
(期日を伝える)
「ここまでは質問ある?」
(質問がないか聞く)
「じゃあ続いて資料の書式だけど、ここに前回の会議時に使用したものがある。」
「この資料と同じように作成して欲しいけど、最近のキャンペーンについても触れるので、その欄もここに入れて欲しい。」
(具体的に伝える・イメージを共有する)
「それぞれの数値を出すためのデータは××にあるけど、宣伝費の欄だけはウチの部署内のデータには載っていないので、宣伝部に問合せないといけない。」
「依頼してから丸2日はかかるので、このあとすぐ先に依頼だけしておいたほうがいいよ。」
「直接出向いて『営業資料に使う今月分の宣伝費お願いします。』と依頼するだけで話が通るようになっているから。」
(つまづきやすいポイントを伝えておく)
「この資料の間違いは許されないので、確実に正しいデータをまとめたい。」
「君が今抱えているほかの資料作成の仕事はいったん置いておいて、この資料の作成を最優先して欲しい。」
(優先順位を伝える)
「私からの話は以上だけど、改めて質問はあるかな?」
(質問がないか聞く)
「そしたら早速取り掛かって欲しいけど、理解漏れとかは無いかな?期限、優先度、参考資料、必要データのありか、注意点について復唱してくれる?」
(復唱させる)
このような形で指示を出せば、部下との認識の違いが生じることもなくなります。
上司としては、「大雑把な指示でも部下に理解して欲しい」と思いたくなりますよね。
実際、部下が優秀な場合は、あいまいに伝えてもなんとかしてくれます。
しかし、「指示が伝わらない・・」と悩む場合は、これくらいの質の指示の出し方をしないと、あとから苦労するでしょう。
適切な指示することの2つの効能
このようにして、部下への指示の出し方を適切に行うことで、あなたと部下との間で認識のズレがなくなり、イライラすることも無ければやり直しを防ぐこともできます。
指示が上手く伝わらず、「部下に理解力がない」と悩むときは、指示の出し方を工夫してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、適切に指示を出すことで、2つのメリットがあります。
部下がその仕事を得意になる
適切な指示によって部下の仕事の成功率が上がり、出来栄えも良くなります。そうすると当然周りから褒められます。
これによって、部下は「自分はこの仕事が得意だ」と感じるようになります。
「得意だ」という意識を持たせることができると、その後同じ仕事を任せてもうまくやってくれる可能性が高くなります。
そして、前向きになりたくさん数をこなせば、あなたの指示が少なくなってもうまくいくようになるでしょう。
結果的にあなたの手間も減らすことになります。
部下自身が良い指示を出せるようになる
管理職が会社の中でさらに出世するためには、自分の部下に成果を出してもらうことが必ず必要です。
大きな成果を出すためには、「人を動かす力」がとても重要です。
そして、「適切な指示の出し方」は人を動かす力の中の重要な要素です。
あなたから適切な指示をされてきた部下は、自分自身が後輩に指示を出すときにも上手く指示をだせるようになります。
そのため、あなたの部下は適切に指示を出すことができ、仕事で成果を上げる可能性を高くすることができるでしょう。
丁寧に指示を出すことは、はっきり言ってかなり面倒くさいです。
しかし、それは後々多くのメリットが生んでくれる可能性を秘めています。
部下に指示が通らない!とイライラするならば、試しに指示の出し方を工夫することをオススメします。