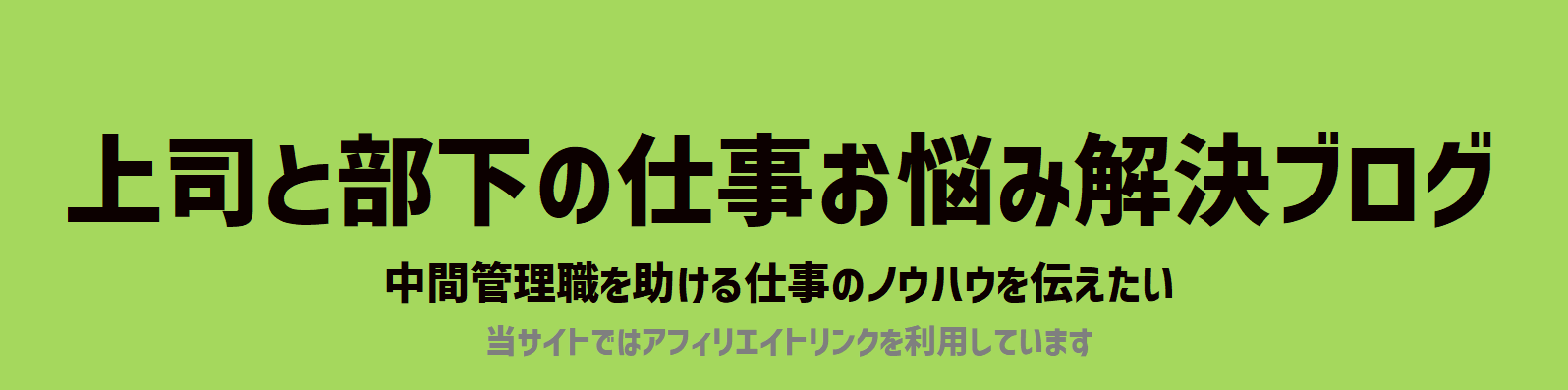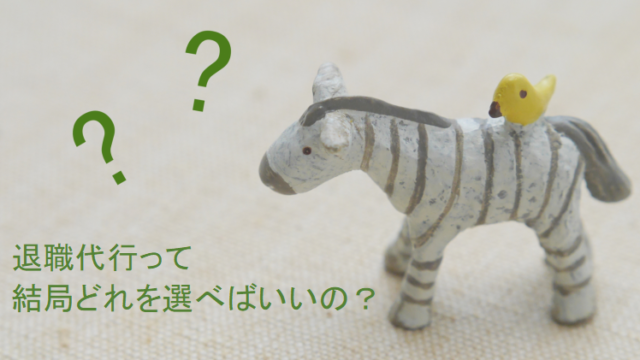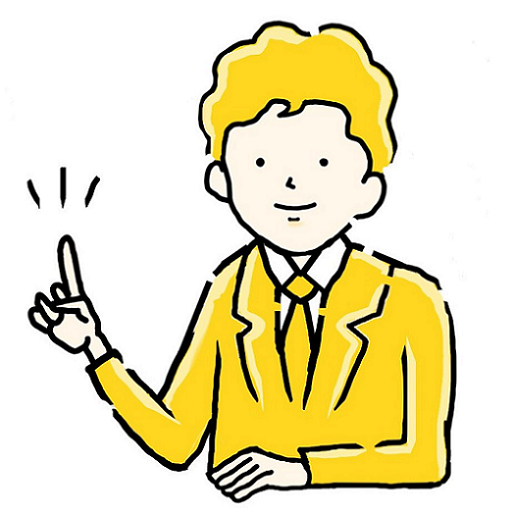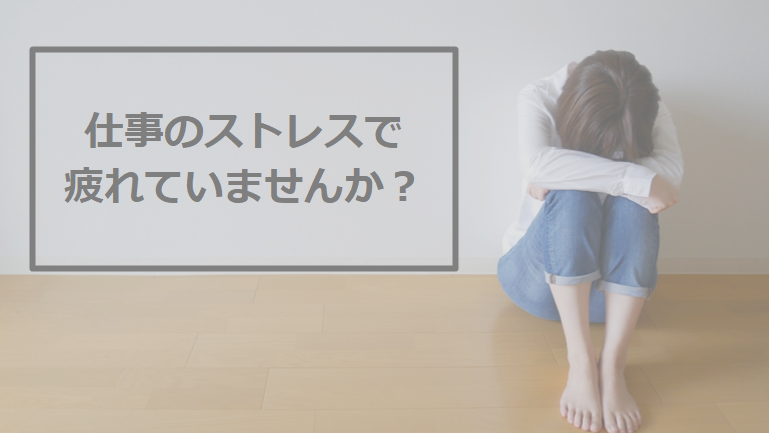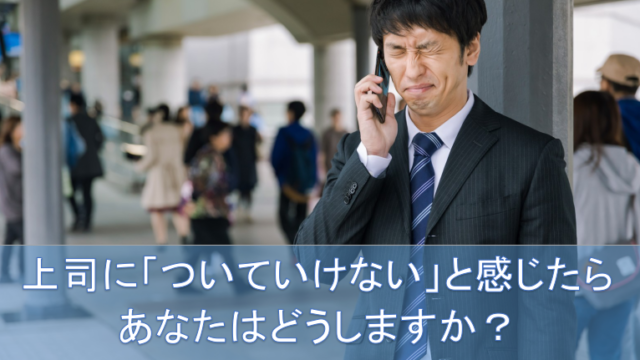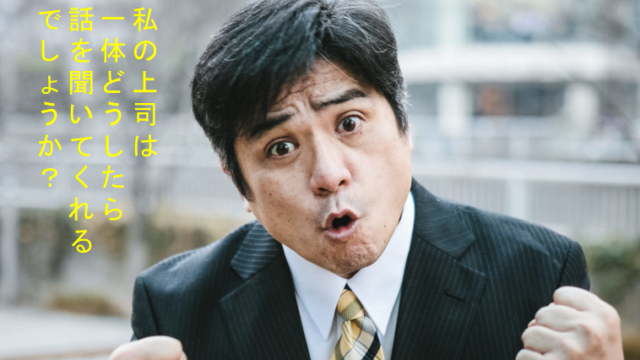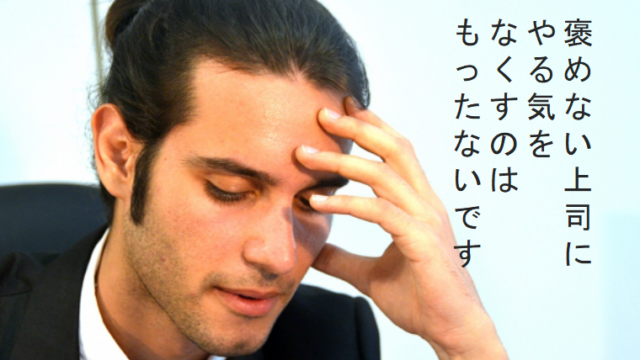- 上司なのに責任をとろうとしない
- 必要な指示を出してくれない
- 甘すぎて部下から舐められる
上司というと頼れる存在であるはずですが、実際には色々なタイプの頼りない上司がいます。
上司が頼りないと、やる気も下がり、「この人のもとで働いていいのか・・」と悩んでしまいます。
そこでこの記事では、頼りない上司のタイプや、上司が頼りないときの対処法についてまとめています。
頼りない上司の性格や能力を変えることは至難の業です。
そんな上司に期待するよりも、あなた自身が変わることで、仕事を上手く回す方が現実的だったりします。
この記事を読めば、上司が頼りない場合にどうしたらよいか分かるので、「上司が頼りない」というストレスや悩みがが軽くなるでしょう。
目次
頼りない上司の5つの特徴

一口に「頼りない上司」といってもさまざまなパターンがあります。代表的な5つの例をご紹介します。
責任を負おうとしない
頼りがいのあるリーダーは、「俺が責任とってやるから、胸を張ってやってこい」と励ましてくれるものです。
しかし、頼りない上司は、「うまく行かなかったら君が責任とってよね」と責任をなすりつけてきます。
また、普通は上司が責任を引き受ける場面(目標未達を責められる時や、クレーム対応のた時など)にて自分が矢面に立たず、誰かに対応させます。
上司がこれでは、部下も「この人についていこう」とは思わず、やる気は下がります。
ビジョンや方針を示さない
部下のやる気を上げる方法として、「ビジョンを示す」というものがあります。
「ビジョン」と一口にいっても色々ありますが、以下のようなものが多いです。
- 会社が目指していることはなんなのか
- 与えられた目標にどのような意味があるのか
- 自分たちの部署の仕事には、顧客や会社にとってどんな意義があるのか
前向きな内容であればどのようなものでもいいですが、ビジョンを上司が直接、自分の言葉で語ることが大切です。
頼りない上司には、そのようなビジョンや方針の説明が一切ありません。
なんとなく「頑張っていこう」という精神論で終わることが多々あります。
人は「○○のために頑張る」というのがあったほうが努力できるものですが、頼りない上司はそれを部下に与えられません。
具体的な業務の指示をしない
「仕事のやり方は任せるよ」といって、具体的にどう仕事をするかの指示を与えないパターンです。
具体的な仕事内容が分かっている場合は、任せる振り方で問題ありませんが、未経験の仕事や自信がない場合には、具体的な手順を伝えるべきです。
新人や経験が浅い人にやり方の指示もせず放置するのは、上司としての責務を果たしておらず、部下からは信頼されないでしょう。
叱らない・注意しない
遅刻や怠慢によるミスなど、気が抜けているときには上司は部下を叱らなくてはなりません。
それを、「嫌われたくない」「面倒くさい」という理由で叱らない上司はよくいます。
ダメなことを指摘されないと、「この上司は何をしても許される」思われ、チーム全体の規律がなくなります。
これでは仕事への緊張感がなくなり、仕事ぶりもだらけてしまいます。
自分の意見がない
経営層の言いなりになったり、客の言いなりになったりして、自分自身の意見や「意見を通そう」という姿勢がない上司もいます。
この上司は、自分の意見への反対意見がでたら、それにすぐ乗っかります。
人が良すぎたり、自分の信念が無いため、自分の意見を通そうという気持ちが無いのです。
上司が頼りない時の対処法

では、あなたの上司が頼りない場合は、実際どのように考えたり動いたりすればいいでしょうか。
3つのポイントを紹介します。
上司を変えようとしない
まず大前提として、「頼りない上司は変えられない」ことを理解する必要があります。
部下の働きかけで覚醒することや、上司自身がある日心境が変わるという可能性はゼロではないですが、かなり低いです。
そのため、上司の変化を期待して行動するのは無意味だと考えましょう。
例えば、落ち着きのない子供をおしとやかにするのは、実の親でも難しいものがあります。
人の性格や価値観を変えるのはかなり難しく、そのためにエネルギーを割くのは効率が悪いうえ、非常にストレスがたまります。
自分がリーダーシップを発揮する
仕事において、上司が頼りなくても成果を上げることはできます。
上司以外の人がうまくリーダーシップを発揮して、周りを巻き込んで仕事をすれば、成功することは十分可能です。
「上司じゃないとリーダーシップは発揮できない」というのは思い込みです。
上司が頼りないなら、いい意味で開き直り、あなたが積極的に周りに協力を仰ぎながら仕事を進めてみるのも一つの手です。
表だってリードするのが不安なら、上司をさりげなくフォローする方法も効果的です。
- 「来週のプレゼンの件、資料できていますか?お手伝いしましょうか?」
- 「後輩の○○君が仕事の進め方で困っていたので指示をしておきました」
のように、上司の仕事が抜けないようアラートをかけたり、起きそうな問題を先回りして解決するという手もあります
「ストレスを与えてくる上司よりはマシ」と考える
上司が頼りないとイライラしますが、なかにはもっと悪質な上司もいます。
- パワハラやセクハラを当たり前にしてくる
- 部下の手柄を横取りする
- いつも不機嫌で感情的にあたられる
など、例を挙げればキリがありません。
こういう上司は、あなたに直接的なストレスをあたえてきます。
頼りない上司は、確かにイライラさせられたり、仕事を回しにくいという問題がありますが、「ストレスを与えてくる上司よりはマシ」と考えることもできなくはありません。
多少無理やりでも前向きにとらえて、リーダーシップを発揮できないか挑戦してみるのもいいのでは、と個人的には思います。
自分が頼れるリーダーになるチャンスでもある

ここまで紹介してきた通り、頼りない上司に悩むときの一番の解決法は、あなた自身がリーダーシップをとってみるという方法です。
会社組織では、上司以外の誰かがリーダーシップを取って成功するケースは珍しい話ではありません。
仕事を何とか成功させたいなら、あなた自身がリーダーシップを取るという選択肢も十分ありです。
そしてこの経験は、あなたが本当に上司になり、リーダーになったときに大きな財産になるでしょう。
頼りない上司の代わりにリーダーとなることで、「どんな上司になってはいけないか」を知るだけでなく、「どのような上司になるべきか」の実感をつかめるでしょう。
リーダーなんてまっぴらごめんなら異動や転職を

とはいえ、全員が全員、自分がリーダーになりたいわけではないでしょう。
そんな場合、代わりに頼れる人が現れてくれればいいですが、そんな都合よくいくとは限りません。
そんな場合は、今の環境から抜け出すのが無難です。
まずは社内で移動ができないか考えてみましょう。人事権があり、頼れそうな上司に相談してみるのも手です。
異動の希望が叶う見込みがなかったり、仕事内容は変えたくない場合は、転職するという選択肢もあります。
とはいえ、転職に自信が無い場合は、転職エージェントに頼るのがいいでしょう。
エージェントを利用すれば、あなたの経歴と希望を伝えれば、それに合った求人を紹介してくれます。
また、面接や書類選考のアドバイスももらえるので、自分だけで転職活動するよりも成功する可能性が高まるでしょう。
数あるエージェントサービスの中でも、親身なサポートで評判なのは「dodaエージェントサービス」です。
また、若年層の転職に特化しているのが、「ハタラクティブ![]() 」で、第二新卒や20代ならばこちらがオススメです。
」で、第二新卒や20代ならばこちらがオススメです。
なお、いきなり転職は不安・・という人は、少しづつ転職活動を始める方法もあります。
頼りない上司には頼らないことが一番
頼りない上司の特徴や対策についてご紹介してきました。
頼りない上司には色々な特徴がありますが、その一番の対策方法は「そもそも頼らない」ということに尽きます
「上司はこうあるべきだ」とあなたの理想を上司に押し付けても、現実は何も変わらすただイライラするだけです。
それよりは、あなた自身の行動を変えてみるほうが、うまくいく可能性は高いです。
とはいえ、リーダーシップは取りたくないという人は、環境を変える方法も効果的です。
- 親身なサポートで評判なエージェントサービス「dodaエージェントサービス
」
- 20代や若手社員の転職サポートに特化している転職エージェント「ハタラクティブ
 」
」