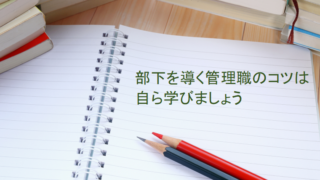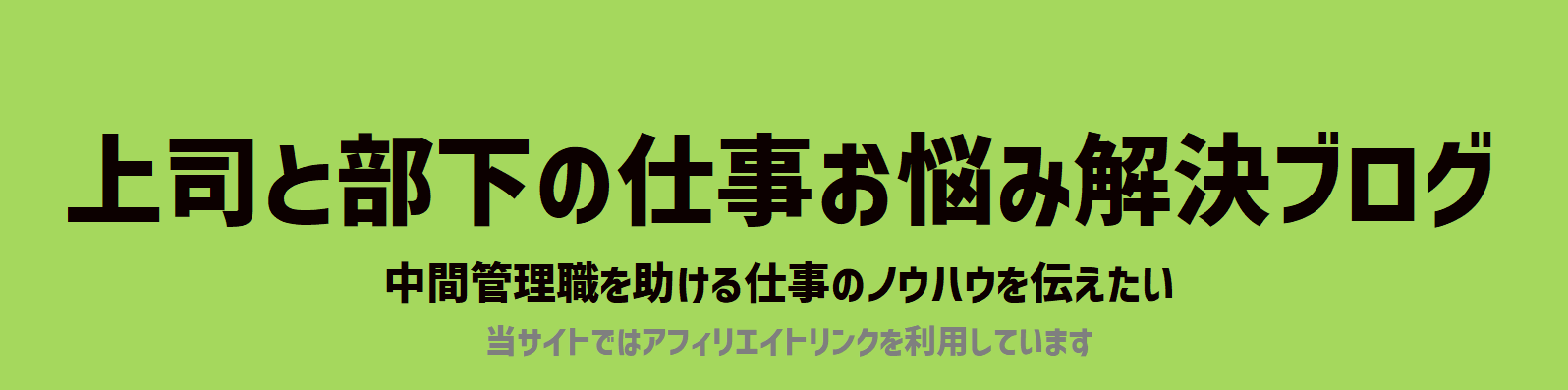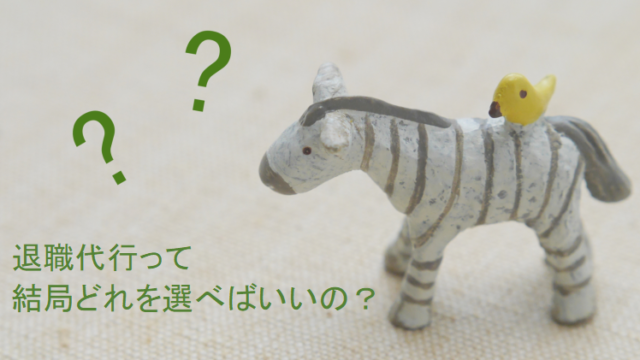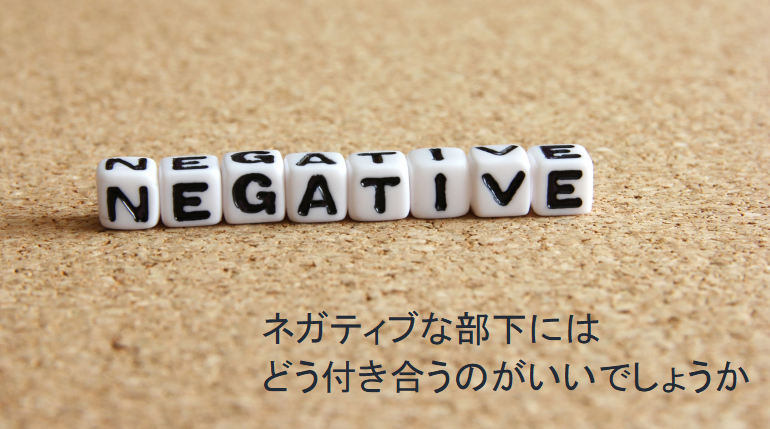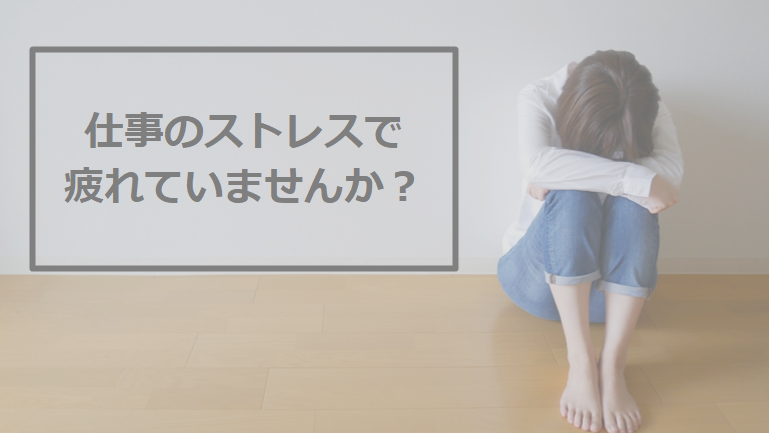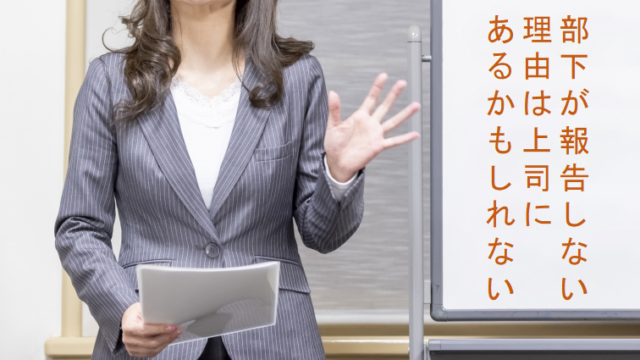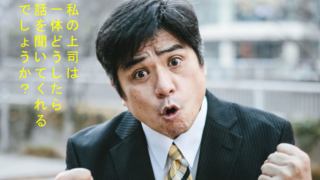ネガティブな部下がチームの雰囲気を悪くすることはないでしょうか?
口ぐせが「無理です」「できません」「こういうリスクがありますよね」で、チームでの動きにブレーキをかけてしまう人がいます。
チームを引っ張る上司としては、こういう存在には手を焼くものです。
このようなネガティブな部下は、相手を認めてあげ、話しを聞き、気持ちを前向きに促してやることが重要です。
またネガティブなのはマイナスばかりではありません。そのプラスの部分も知り、活用することでより成果の出しやすいチームになるでしょう。
今回はネガティブな部下の対応と活用の方法についてまとめました。
ネガティブな部下に手を焼いている人は参考にしてください。
ちなみに、仕事のストレスで疲れている人に、おすすめ癒しグッズを紹介しています。
部下からのストレスで疲れている人は、よかったら参考まで。

目次
ネガティブな思考をする部下の背景
では、ネガティブな部下は、なぜネガティブな言動をしてしまうのでしょうか。
これには主に2つの理由が考えられます。
①プライドと自信がつりあわない
イソップ物語のなかで、「すっぱいぶどう」という物語があります。
物語の内容は以下のようなものです。
キツネが、たわわに実ったおいしそうなぶどうを見つける。
食べようとして跳び上がるが、ぶどうはみな高い所にあり、届かない。
何度跳んでも届かず、キツネは怒りと悔しさで、「どうせこんなぶどうは、すっぱくてまずいだろう。誰が食べてやるものか。」と捨て台詞を残して去る。
出典:Wikipedia
そして、その解説は以下のように紹介されています。
手に入れたくてたまらないのに、人・物・地位・階級など、努力しても手が届かない対象がある場合、その対象を「価値がない・低級で自分にふさわしくない」ものとみてあきらめ、心の平安を得る。
出典:Wikipedia
この物語では、対象(ぶどう)を「価値がない・低級で自分にふさわしくない」と判断しています。
一方で、ネガティブな人は、逆に「自分側に価値がないのだ」と判断することで心の平穏を保つのです。
ネガティブなことを言う人は、実はプライドが高いパターンが多いです。
プライドが高いがゆえに、失敗してしまったときのネガティブな気持ちに整理をつけられません。
そこで、「どうせこの仕事は(自分には)上手くできない」と考えて、自分を納得させているのです。
このような発言をしておいて、本当にできなかった場合は「ほら、自分の言った通りだ」なり、逆にできた場合は「難しいのにできたなんてすごい」という印象になります。
これが、「できる、大丈夫」と言っているのにできなかったときは非常に恥ずかしくなりますよね。
このように、ネガティブな発言によって自分のプライドを守っているのです。
②思考のクセがついている
一度ネガティブな考え方が根付いてしまうと、すべてのことにおいて「できない理由」「リスク」を考えてしまいます。
物事には色々な捉え方があります。例えばコップ半分に入っている水を見て、「まだ半分もある」と感じるか、「もう半分しかない」と感じるかは、その人の感じ方次第です。
ネガティブな部下は、すべてのことにおいてネガティブな思考にとらわれるので、何を見てもまず悲観的に考えてしまいます。
ネガティブな部下はこのような背景で、ネガティブな思考・発言をしてしまいます。
本人は「周りの士気を下げてやろう」だとか「失敗させてやろう」という理由でネガティブな言葉を発しているわけではありません。
プライドの高さから失敗に敏感だったり、ネガティブに考える習慣がついてしまったために、ネガティブな言動をしてしまうのです。
ネガティブな部下への対応法
 では、このようなネガティブな部下へのどのように対応するのがよいのでしょうか。
では、このようなネガティブな部下へのどのように対応するのがよいのでしょうか。
ここでは3つの方法をご紹介します。
①聞いて受け入れてあげる
本人のネガティブな意見を一通り聞いて、受け入れてあげましょう。
そもそもネガティブなことを言うのは、「仕事をちゃんとやりたい」という気持ちの裏返しです。
いい加減な人間は楽天的に考え、ネガティブなことは言いません。
ちゃんとやりたいからこそ不安な点が気になったり、自分のことを下げようとするのです。
そのため、このようなタイプのネガティブな発言は、本当に反対しているというよりは、心の整理をつけるためだけのものです。
そう考えれば、ポジティブな人の「よし!」「いくぞ!」というような掛け声と大きな違いはありません。
なので、ネガティブ内容にいちいち目くじらを立てることに意味はありません。
相手の思いを聞いてやり、共感を示してやることで自然とやる方向になっていきます。
②認めてやる
先ほどからご説明している通り、ネガティブな部下は、高いプライドのわりに仕事に自信がないことが多くあります。
そこで、頻繁に褒めてやり励ますことで自信をつけさせるのも有効です。
しかし、プライドが高い分、見え透いたお世辞には敏感で「そんなこと言われてもどうせ俺なんか・・」とネガティブな言葉で跳ね返されることがあります。
このとき、
・具体的な点について褒める(仕事が他の人より速かったり・資料の情報が詳しい、など)
・当たり前のことをちゃんとやっていることを褒める(毎日欠かさずにキレイに掃除をしている・書類の不備がほとんど無い、など)
ことを意識しましょう。
また、「自分は役に立っている」という実感を持たせることも重要です。
細かい性格であれば事務処理を任せたり、考えることが得意なら情報の分析を任せるなど、ほかのポジティブな人が苦手になりがちな仕事を任せてみるのです。
任せた仕事が上手くいけば、自然と自信がつくものです。
自信がだんだんとついてくると、自分を下げることでプライドを守ろうとする必要もなくなり、ネガティブな発言も減っていきます。
③前向きに変換する
一通り聞いたうえでも、まだあまり乗り気になっていない場合にやるべき方法です。
ネガティブな発言に対して、「そんなこといいつつ、結局頑張るのが君だよね!」「真剣に考えているからこそそういう不安を思いつくんだよね!」と前向きな言葉に変換してあげましょう。
ネガティブな発言をスルーし、前向きなフレーズをかぶせてやるのです。
「確かにそういうリスクもあるね、上手くいかない可能性もあると思う。でもやらないと成功しないし、○○な価値もあるから協力してね」と丸く収めるようなイメージです。
また、ネガティブな部下が話す内容と矛盾する事実を指摘するのも一つの方法です。
ネガティブに考える人は、ネガティブな側面ばかりに注目しがちですが、世の中の多くのことにはニ面性があり、ポジティブ考えられる側面もあります。
そういうところに焦点を当て、「この案件にはこういう良い点もあるよね」ということを伝えてやります。
ころっと考えを変えることは少ないですが、前向きに考え始めるきっかけになるでしょう。
部下からの批判は会社の改善点でもある
ネガティブな部下への対応には、このような点を意識すればよいでしょう。
そして、ネガティブな発言は実は良い面もあるということも触れたいと思います。
ネガティブな部下発言のなかで、「こんなのやってられない」という発言もあるでしょう。
文句言わずに前向きに考えろ!と言いたくもなりますが、このような部下の批判は、ただのわがままではなく、改善が必要な意見である可能性もあります。
ネガティブな部下の意見を無視して仕事を進めた結果、大きな落とし穴にはまるという危険性もあります。
それに対してネガティブな部下は、リスクや不安点を見つけ出すのに長けています。
彼らの意見が、大きなリスクを回避する良い案であることもあります。
そのため、彼らのネガティブな意見はスルーせずに、拾ってみるというのも悪くありません。
そのときには「この視点からは考えてなかったよ、貴重な意見ありがとう」と声をかけてやることで部下を認めてあげましょう。
ネガティブな発言は周りへ感染するリスク
ネガティブな部下にはこのように対応することが大切ですが、注意する必要があるのは「周りへの感染」です。
ネガティブな発言がいつの間にか周りへ移り、チーム全体にネガティブな言葉がはびこるようになると大きな負のエネルギーとなります。
そうなると実際に部下たちの動きも悪くなります。
対策としては、まずは先ほど紹介した行動でアプローチしましょう。
また、周りのメンバーに対して、ネガティブ発言のメカニズム(気持ちの整理をつけるためにネガティブなことを言っている)を説明し、共有してしまうことです。
人は悪意に敏感です。「チームの雰囲気を悪くしよう」という意図でネガティブ発言をしているわけではない、ということが分かれば他の部下はモヤモヤしません。
「彼がネガティブなことを言いはじめるということは、真剣にその仕事に取り組もうと思い始めたということなんだ、どんどん励ましてやれ!」くらいの共通認識をチームに持たせましょう。
そうすることでネガティブな発言をされると周りが一斉に励ましはじめ、逆に明るくなるということも起こりえます。
ネガティブ発言の注意は本人を尊重しながら
なお、感染を防ぐために単純に「ネガティブ発言はやめろ」と注意することも必要です。
「ネガティブ発言を職場で公言することが良くない」というのは、本人も自覚しているものです。
そのため、注意することは悪くないのですが、気をつけるべき点が2つあります。
①発言自体は禁止しない
「他の人がいる前で話されると、士気が下がってしまうからやめろ」という言い方をしましょう。
つまり、「発言自体は構わないが、周りの人に聞かせるな。」ということです。
というのも、ネガティブな発言自体を禁じてしまうと、その人の気持ちの整理がつけられなくなります。
話を聞いてくれるプライベートの友人や家族に話したり、もしくは職場の人が見ない(かつ会社が特定されない)ツイッターでつぶやくなどは良しとしてあげましょう。
②他の人がいる前で注意しない
また、他の人がいる前で注意するのは避けましょう。
このタイプはプライドが高いことは先ほどお伝えしましたが、このタイプが皆の前で注意されると、プライドの高さと自信の低さのギャップがますます開きます。
こうなるとますますネガティブ発言が止まらなくなります。注意するのは個別の場で行い、プライドを傷つけないようにしましょう。
ネガティブ発言は「かわいい」と捉えよう
このように、ネガティブな部下はその特徴をつかみ、チームに悪影響をもたらさないように心がけましょう。
気持ちの整理をつけるために話しているのであれば、ネガティブな発言もかわいく思えるものです。
リーダーがそのような発言を「かわいいもんだ」と思い、明るくいなしてあげることでチームも明るくなります。
「ネガティブなことをいう奴はダメだ」と上司自身がイライラしてしまうのは、それはそれでチームの空気を悪くしてしまいます。それも避けたいものですね。
ネガティブな部下は上手くコントロールして前向きにしてやりましょう。