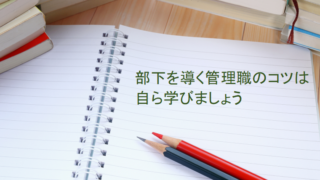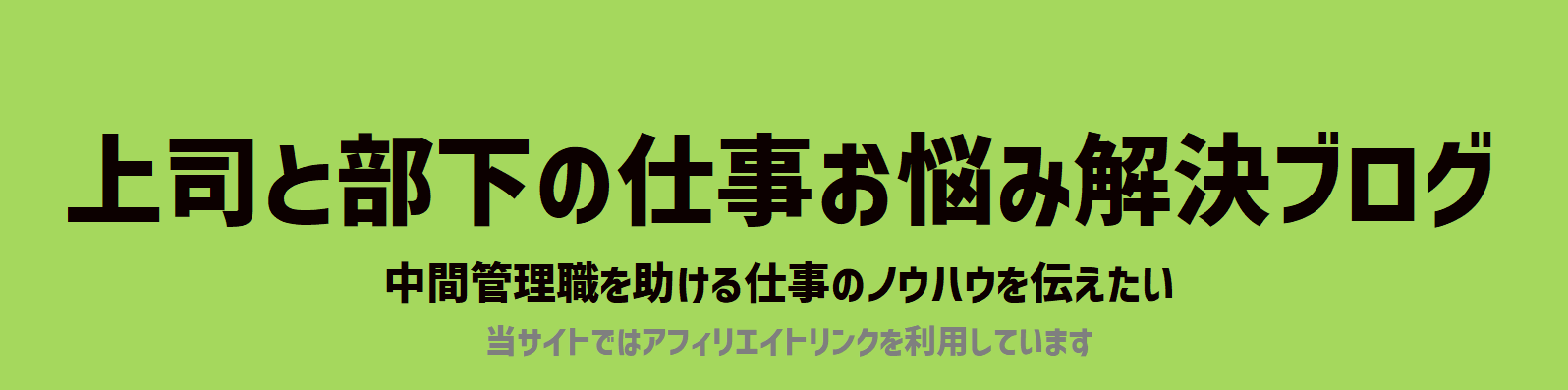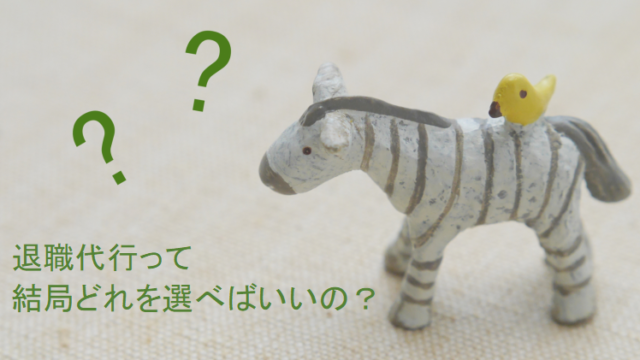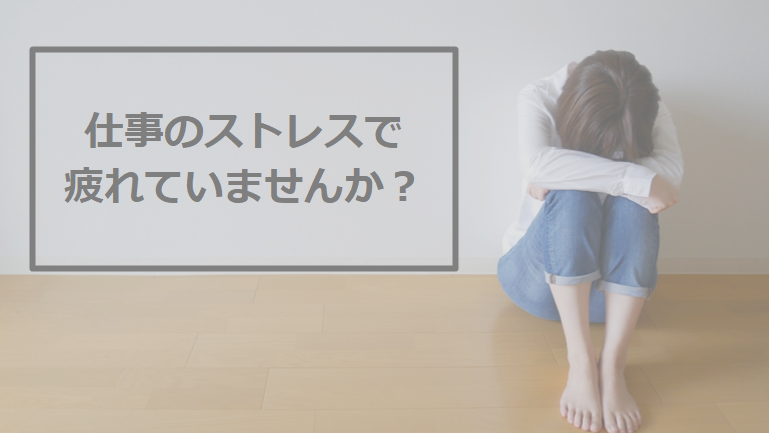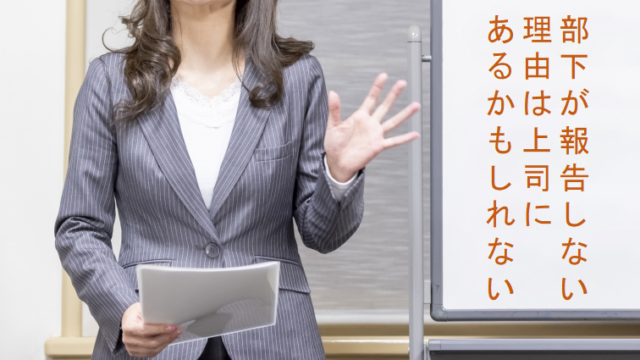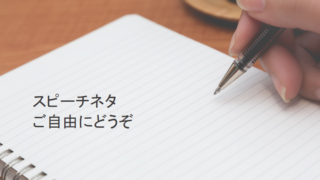要領の悪い部下にイライラしてしまうことはないでしょうか。
部下がミスをしたり、仕事のスピードが遅かったり・・というときには、上司のあなたがカバーすることが多いでしょう。
上司としては器用な部下の方が、教育の手間もかからず楽なものです。出来れば要領の悪い部下は持ちたくないと思うかもしれません。
こういう部下は、同じように教えているのに、他の部下と同じようにできない・・という姿を見るとイライラする気持ちにもなるでしょう。
しかし、だからといって見捨てるわけにもいかず、上手く育てていくことが上司には求められます。
こういうタイプの部下には、上司がそれに合わせて接することで育つかそうでないか変わります。
このタイプに合わせた育成方法を押えることで、要領の悪い部下を育てることができます。
また、要領が悪いと思われる部下でも、後に成長して立派な戦力になる人もいます。新人のときに要領が悪いからと言って、その部下に能力がないと決め付けるべきではありません。
「こいつはダメだ」と見限る前に、以下の内容を読んで、部下との向き合い方を考えてみてください。
ちなみに、仕事のストレスで疲れている人に、おすすめ癒しグッズを紹介しています。
部下からのストレスで疲れている人は、よかったら参考まで。

目次
「出来の悪い部下」の特徴
まずは、上司から見て「出来が悪い」「要領が悪い」と感じる部下の特徴をご紹介します。
この特徴に当てはまる部下は、他の部下とは違った接し方をするほうが効果的な可能性が高いです。
①仕事が丁寧すぎる
仕事が丁寧であることは良いことですが、必要以上に丁寧である必要はありません。
例えば、資料の作成を求められた場合、文字のフォントや配色について30分や1時間かけて悩むのは明らかに効率が悪いと言えます。
また、仕事ではすべてのことに全力を出す必要はなく、重要性の低いことには丁寧さよりも早さを優先してこなすことが重要です。
しかし、要領の悪い部下はこのことが分からず、すべてのことに対して全力で完璧に仕上げようと考えてしまうため、無駄に丁寧に仕事をしてしまいます。
その結果、仕事のスピードが遅くなり、要領の悪い仕事になってしまいます。
②優先順位がつけられない
このタイプの部下は、すべての仕事に全力で取り組むため、仕事を引き受けた順番にすべて全力で取り組む傾向もあります。
しかし、仕事には優先順位というものがあり、その日中にやりきらなければいけないこともあれば、一週間後に仕上げればよいものあります。
さらには、「時間があるときにやればいい」というレベルの仕事もあります。
これがわからないと、取り組む仕事の順番がめちゃくちゃで、急がないことを先にやり、至急対応すべきことを後回しにしてしまう・・という事態になります。
③言われたことをきちんとやるが、それ以外のことはできない
真面目な性格なので、言われたことはきちんとこなします。
しかし、臨機応変にやり方を変えるということが苦手です。このタイプは冗談も真に受けてしまうことがあります。
つまり、言われた言葉を額面どおり受け取りやすい傾向にあり、建前と本音の区別をつけるのが苦手です。
仕事についてもそれと同じで、言われたこと以外に必要なことを先回りしてやったり、指示された内容を違う方法でやるということが苦手です。
また、このようなタイプは、イレギュラーな事態に対応することも苦手です。
要領が悪い人への指導方法
では、このような要領の悪い部下に対しては、どのように接するとよいのでしょうか。これには5つのポイントがあります。
①優先順位を示す
何を優先して、何を後回しにするのかということは、仕事それぞれの締め切りと重要性をもとにその都度判断するものです。
経験が豊富だったり、適切な判断力のある部下であれば自分で順位付けができますが、そうない場合はやはり上司から示すしかありません。
毎日、抱えている仕事の状況を確認したうえで優先順位を判断するか、新しい仕事を振るときに優先順位を指示しましょう。
その際には、優先順位付けの根拠や理由も一緒に伝え、だんだんとその部下自身で優先順位付けができるように教育することも重要です。
②仕事のやり方を明確に伝える
このタイプの部下は、自分で考えて動くことが苦手です。
そのため、仕事の一つ一つの手順を明確に示することが必要です。「適当にやっておいて」だとか「自分で考えてやってみて」という抽象的な指示では動けません。
やり方を示す→上司が実際にやってみせる→部下に一人でさせてみる→出来ているかチェックする
という流れで教えてやる必要があります。
③仕事の目的や意義を教える
これは自分で応用を利かせるために必要なことです。
例えば、接客の仕事において、お客様をもてなすための動作一つ一つについてその意味があるものです。
ご老人に向けた接客のマナーもあれば、女性に対してやるべきこともあると思います。
そのような一つ一つの接客動作の目的が分かれば、男性客に対してと女性客に対して行う動作を自分で考えて変えられるはずです。
このように、どんな仕事についてもその目的や意味を伝えることが出来れば、仕事一つひとつについて「目的を達成するためにどうすべきか」を考えることができます。
その結果、臨機応変に仕事のやり方を変えることが出来るようになります。
④手の抜き方を教える
すべての仕事に100%の力を出すことが大切ではなく、丁寧さよりもスピードが求められることも多くあります。
仕事の目的とは関係の無いところでは、丁寧さは必要はありません。
例えば、上司に資料作成を求められたとき、その資料が会議で配布するようなのか、それとも上司自身が発表する際のカンペとして必要なのかによって必要な丁寧さは異なります。
カンペとして作成する場合は、資料のレイアウトや見た目の作成には手を抜いても構いません。それよりも早く仕上げることが重要です。
このように、仕事の目的によって手を抜いてもよいことがありますが、このタイプの部下はそういうことを自分で気づくのが苦手ですので、上司から教えてやらなければいけません。
⑤自信をつけさせる
このタイプの部下は周りから叱られたり責められることが多く、そのため自分に自信がないことがあります。
そのため、本当は自分で気がついているにもかかわらず、「余計なことをして怒られてしまうのではないか」と不安であるため、言われたことしかできないこともあります。
こういう場合は、まず部下ができた仕事に対して「褒め、励まして自信をつけさせる」ということがとても大切になります。
真面目に仕事をしてくれていることに感謝の気持ちを伝えたり、もし部下が自分で考えて動くことがあれば、それもきちんと拾ってあげて褒めてやります。
もし自分で動いた仕事が間違ったものであれば、自主的に動いたこと自体は褒めてやり、なぜその仕事が違うのかを丁寧に伝えてあげましょう。
これによってその部下は同じことを繰り返さなくなりつつも、自分で考えて動くことは止めません。
このように声をかけて部下に自信をつけさせることで、応用を利かせて仕事することが出来るようになります。
仕事が出来ない部下への対処方法
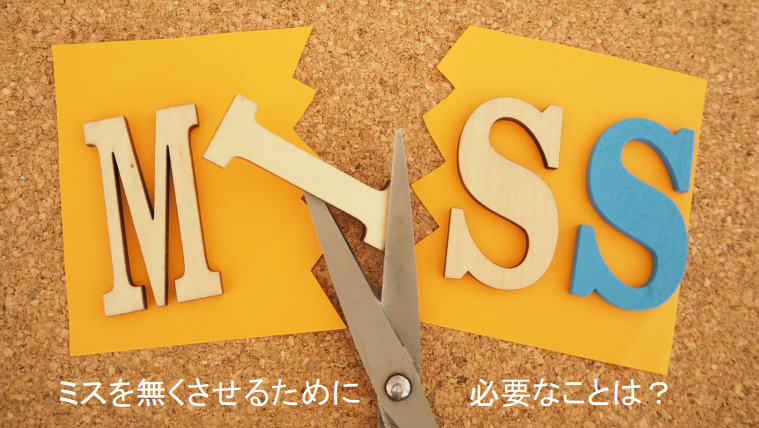
要領の悪い部下には、以上のような接し方を心がけることで育てることができますが、そのためには信頼関係を築くことも重要です。
と言うのも、上司から叱られることで信頼感が崩れ、部下が仕事でつまづいていることを共有できないことがあります。
上司への不信感が高まったり、「また怒られたらどうしよう」という不安から、声がかけにくくなることもあるのです。
そういう場合には、部下がつまづいている点を部下から拾い、共有することが最も重要です。
そのため、本人とざっくばらんに話し、「どこでつまづいているか」というのをヒアリングしたいところです。
このとき、本人もうまくできない罪悪感から萎縮してしまい、自分の能力だけに問題があると思い込んでいることが多く、簡単に聞いても出てこないことがあります。
そこで、相手を責めるような口調ではなく、
「今うまくいっていないのは、あなたのせいではなく、教え方が合っていないからという可能性がある。」
「具体的にどこでつまづいているかがわかれば、違う方法で教えることができるので、自分なりに苦しんでいるところを聞かせてくれないか」
というスタンスで話を聞いてみればいいでしょう。それを聞くことでがきれば、内容に合わせて教え方を調整できるでしょう。
このようにして、部下を育てるためには、接し方を変えるほか、部下がつまづいているポイントを共有することも重要です。
できない部下へのストレスとどう向き合うか
以上のような接し方によって、要領が悪い部下を育てることができます。
しかし、器用なタイプの部下よりも育成に手がかかり、時間もかかるのも事実です。育てていく中でイライラしてしまうことも多々あるでしょう。
上司としてはそのときにどのように考えるべきでしょうか。
まず、上司である以上、部下を育てるのは仕事のうちの一つに入ります。育てるのが上手な上司はどんな部下もうまく戦力にして成果を出します。
上司として仕事をする以上は、部下の育成に責任があります。手がかかる部下を育てるのは自分の修行だと考えて取り組むことが必要でしょう。
また、こういうタイプの部下に対してイライラが募り、大声で怒鳴ったり罵倒してしまう上司もいますが、それは上司が自分の感情をコントロールできていない証拠です。
必要に応じて大声で叱ることもあるでしょうが、イライラを発散するような形で罵倒してしまうようでは上司として失格です。
このような行為は、周りの人に対して「自分はダメな上司です」と言いふらしているようなものだと心得ましょう。
なお、上司としては「もっと有能な部下だったら仕事が上手くいくのに・・」と考えてしまうことがあるでしょうが、それはただの甘えだと思ったほうが賢明です。
どんな業種のどんな部署でも、理想的な人員で仕事ができることはまれです。
普通は採用コストや人件費に限りがあります。そのため、今あるメンバーを上手くやりくりして成果を出すことが求められます。
本当に優秀な上司は、部下が有能だろうとそうでなかろうとも、今あるメンバーや資源を有効活用して成果を出すものです。
そのため、「部下が優秀だったら・・」と嘆くよりも、「今あるメンバーでどう成果をだそうか」と考えたほうが実際に成果がでるものです。
要領の悪い部下が将来有望である理由
このように、要領の悪い部下は上司にとって最初はストレスになってしまうかもしれませんが、このタイプの部下は将来有望な面もあります。
というのも、自分が要領が悪かった部下が後輩に仕事を教えるときに、非常に心強くなるものです。その理由となる点を2つご紹介します。
①要領が悪い後輩の気持ちが分かる
自分自身が仕事を上手くこなすために苦労した人は、そのときの悔しい気持ちも味わっています。
そのため、将来自分が後輩を教育するときに、教える相手が同じようなタイプの場合、その心情に寄り添うことができます。
どんな言葉をもらうと発奮するか、またどんなこと言われるとやる気が下がってしまうかなどが自分自身の経験からわかるものです。その分効果的な声かけができるでしょう。
また、教える側が苦労した経験を伝えることで、教わる側も共感し、「この人もかつては苦労したのか」と前向きになります。
逆に、教える側が器用なタイプだった場合、要領の悪いタイプの部下を教えるときに「なぜこんなことができないのか」という考えが頭をよぎります。
それがもし表に出てしまった場合、教わる側としては不信感を感じたり過度なプレッシャーに感じたりとマイナスに作用します。
②つまづきやすいポイントと具体的な対処法が分かる
上手く仕事ができるようになるために苦労したということは、多くのポイントでつまづいたということです。
そしてつまづいたポイントが多いということは、その具体的な対策方法を持っているということにつながります。
苦労なく成果を出した人はつまづきやすいポイントと、その対策方法の引き出しが少ないものです。
この場合、教える相手がつまづいていても、その対策方法をうまく教えることができず悩むことになりがちです。
最悪の場合は「なんとなくやればできるでしょ」としかアドバイスできない可能性があります。
これでは教わる方は上達しないどころかモチベーションが下がります。
それに対して、自分自身が要領が悪く、苦労した経験が多く引き出しが多い人は、その経験を元に、同じような部下に効果的に教えることができます。
このような点で、かつて「要領の悪い部下」と思われていた部下が、後輩を教えるときに活躍してくれる可能性があります。
スポーツの世界で言われる「名監督名選手にあらず」という言葉を聞いたことがある人もいるかと思います。
これは選手として優秀な成績を収めた人が必ずしも監督として同じように成功するとは限らないという意味です。
プレーヤーとして優秀な人でも、部下を育てられるとは限らない一方で、選手としてはそれほどでなくても、部下を成功されられる人もいる・・ということが言えます。
これはスポーツの世界に限ったことではなく、仕事の世界についても同じです。
自分が優秀で成果を挙げるのに苦労しない社員は、他の人の苦労が分からないことが多いため、教育係としては要領の悪い部下の方が上手くいくことが多いものです。
そういう意味で彼らは将来有望だと言えます。
そういう部下がいた場合、試しに新人の教育係に任命してみてもいいかもしれません。
ただし、教えることも苦手なようなら避けた方がいいですが・・
一生懸命な部下は要領が悪くても大成する
以上のように、要領の悪い部下の特徴や育成方法、有望な点についてご紹介してきました。
上司としてはイライラしてしまうこともあるかもしれませんが、上司自身の指導スキルの向上させるための試練として捉えてみてください。
たとえ要領が悪く、周りから「出来ないやつだ」「彼は使えない」という評価をされたとしても、その部下が一生懸命仕事に向き合う限りは、時間がかかっても大成してくれます。
そして苦労して成長してくれた部下は、将来同じようなタイプの部下に対しても上手く指導することのできる有望な社員になってくれます。
「こいつはダメだ」と勝手に見限るのではなく、要領が悪かろうとも、その部下の可能性を信じて教えるのが優秀な上司です。