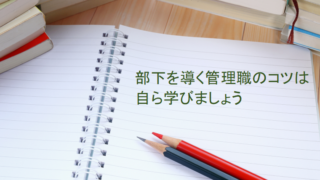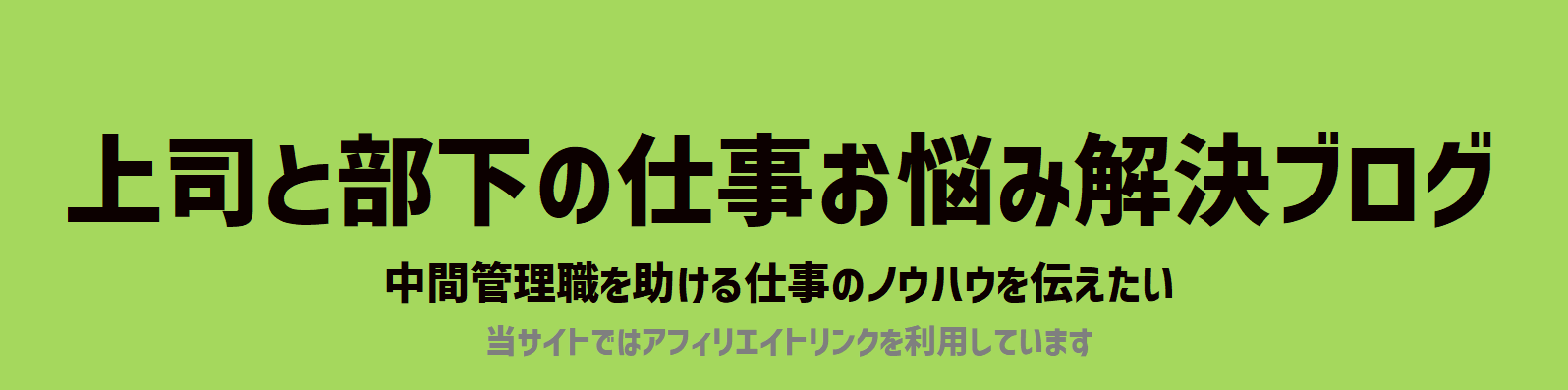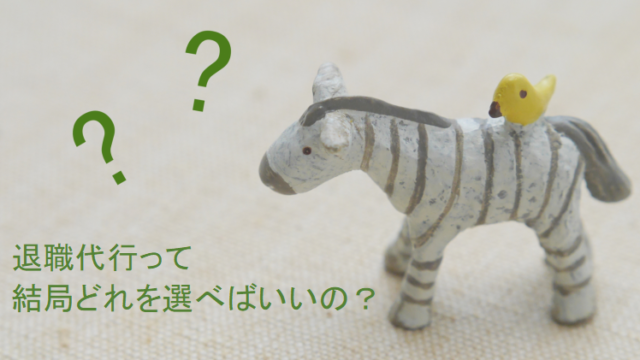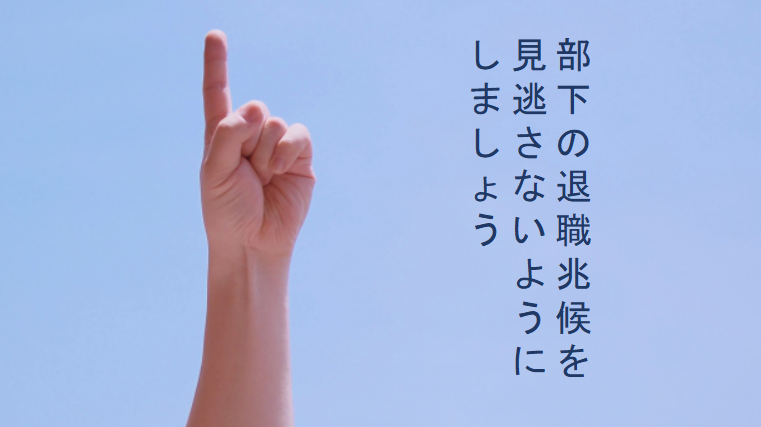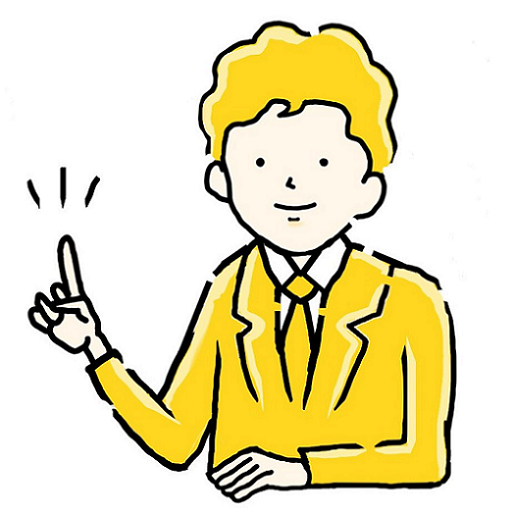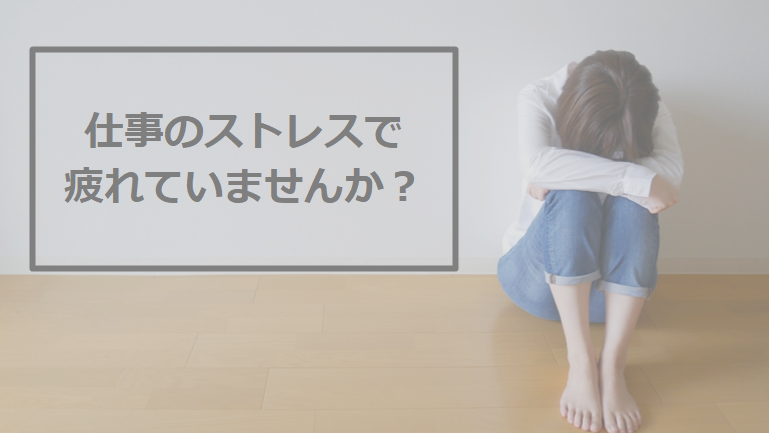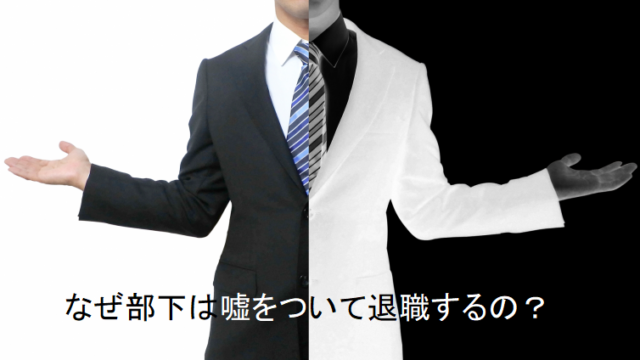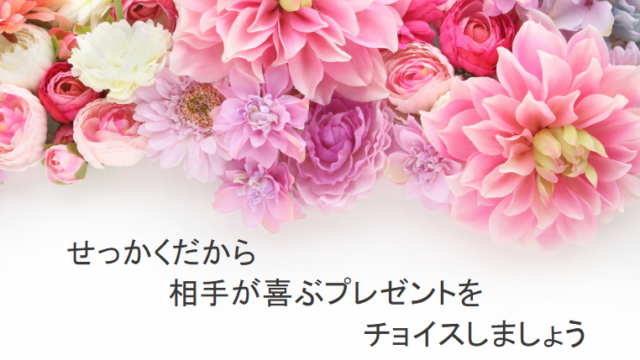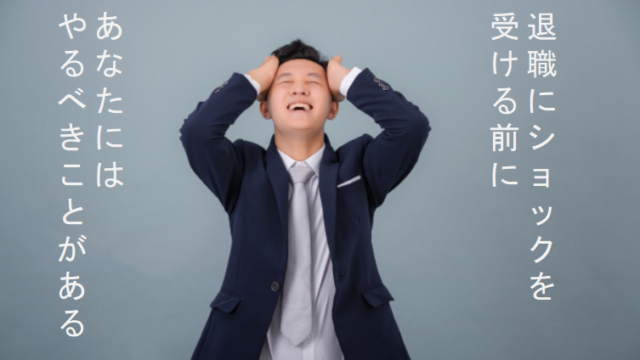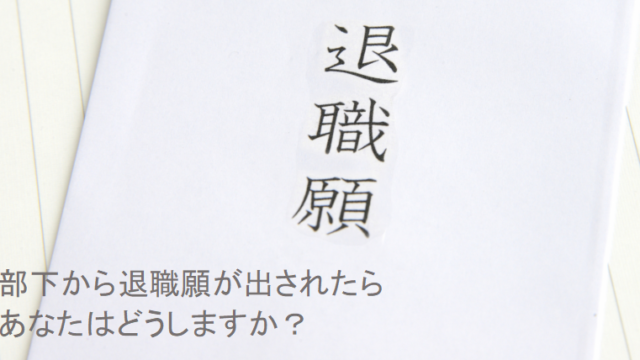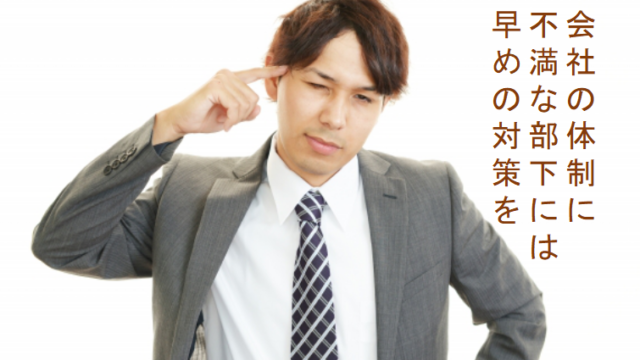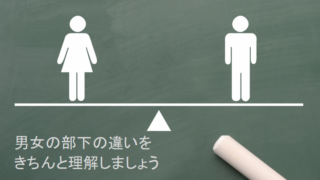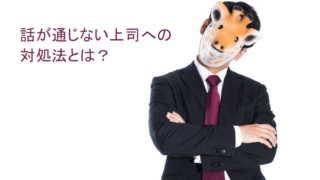上司としては、部下に退職されてしまうと苦労することが多いものです。
しかし様々な理由で、日々色々な職場で部下の退職が発生し、多くの上司を困らせています。
部下が退職を考えるときには、心の中で納得できない不満が時間をかけて積み重なり、限度まで来たら退職を決意し、転職活動をはじめます。
そのような行動をとる部下には必ずそのその「兆候」というものがあり、それを察知することがとても大切です。
本気で退職を考えている人ほど、こっそり退職の準備をはじめるため、退職の兆候は上司が意識しないと見落としてしまいます。
そうなると退職を引き止めることは難しいでしょう。事前に上司から声をかけ、退職という決断をされないようにフォローしなければいけません。
これからご紹介する、部下の退職の兆候に敏感になることで、退職を言い出される前に上司が先手を打つことができます。
目次
段階別に表れる部下の退職サインとは
退職を考える部下の兆候には、さまざまなものがあります。
そして、そうした「兆候」というのは、部下がどの「段階」にいるかで異なります。
部下が上司に退職を申し出る前には、以下のようなステップを踏むことが多いものです。
- 退職を決断する
- 転職活動を開始する
- 内定をもらい、退職を申し出る準備をする
部下がどのステップにいるかによって表れる兆候は違います。段階別の兆候を知り、退職の申し出を受ける前に対処をしましょう。
退職を決断したときのサイン
実際に退職する部下は、必ず「退職しよう」と決断するタイミングがあります。
その決断をした後は、以下のようなサインが見られます。
不平不満を言わなくなる
それまで会社の不満をグチグチ言っていた人が突然言わなくなった場合は、今の職場に見切りをつけたからという可能性が高いです。
「辞める」と決めてしまえば、今の職場への関心がなくなります。
会議時の発言が減った
退職を決断した場合、仕事内容にも関心がなくなります。そうなると会議での発言も減ってしまうものです。
会議だけでなく、仕事に対する情熱ややる気もなくなり、自分から何かを提案することもなくなります。
世間話に参加しない
同じように、職場の人間関係にも関心がなくなります。それによって社員間の世間話にも興味を示さなくなります。
飲み会への参加率も減り、職場で孤立気味になることもあります。
転職活動を開始したときのサイン
部下が退職を決断した後、実際に退職を申し出る前に、転職活動を始めることが多いものです。
その時は、①でのサインに加えて以下のような兆候も見られます。
身なり、服装が変わる
髪型をこざっぱりさせたり、スーツで勤務していない人がスーツやジャケットを着るようになった場合、面接への準備をしている可能性が高いと言えます。
また、応募企業からの電話なども増えてくるため、時には勤務中にコソコソ電話応対する様子が見られることもあります。
残業をしなくなる
プライベートの時間を今の仕事よりも転職活動に優先させることが多いため、残業をしなくなります。
仕事の指示や依頼に対しても、乗り気でなかったり、嫌がるそぶりを見せることもあります。
遅刻や早退が増える
会社の面接を受けたり説明会に参加するために、遅刻や早退をすることが増えていきます。
残業をしなくなるのと同じように、今の会社で働く時間よりも、転職活動にかける時間を優先するためにこのような兆候が見られます。
内定をもらい、退職を申し出る準備をしているときのサイン
採用内定をもらって退職の申し出の準備を始める部下は、実際に退職するまでの動きを想像し、その準備を着々と進めるような兆候が表れてしまいます。
具体的には以下の通りです。
新しい仕事に関心を示さない
退職を決意しているので、当然これ以上今の会社の仕事に関わるわけにはいけません。
そのため、新しい仕事の話を振られても、あからさまにはぐらかしたり他の人に押し付けたりします。
有給の消化が増える
退職の際には有給消化を希望することが多いですが、会社から指示される引継ぎのスケジュールによっては上手く消化できないことがあります。
そのため計画的な社員は、退職を申し出る前から少しずつ、何かしらの理由をつけて有給を消化します。
引継ぎマニュアルを作る
退職の際には引継ぎが伴います。何も指示されていないのに、勝手に引き継ぎマニュアルを作り始める場合は、退職の引継ぎに向けて準備していると考えてよいでしょう。
部下の退職の引き止めには早期対応が必要
このように、部下が退職する兆候には、その段階に応じて色々なものが見て取れます。
大切なのは、早い段階での兆候に気づき、声をかけることです。
先ほどの「内定をもらい、退職を申し出る準備をしているという段階」になってしまった場合は止めるのはほぼ不可能と考えたほうが良いでしょう。
遅くとも、「転職活動をはじめた段階」で発見することが必要です。
このとき、部下の様子を見て、そのような兆候が見られた場合は、「最近疲れないか?何か抱えていることない?」と声をかけましょう。
そしてご飯に誘うか面談の機会をとり、二人っきりで話す機会をもうけましょう。
転職活動をしている段階までで、部下から「退職を考えていて・・」という話を引き出すことができれば、まだ引き止められる可能性が高くなります。
なお、部下から退職を切り出されたときの対応は、こちらが参考になります。
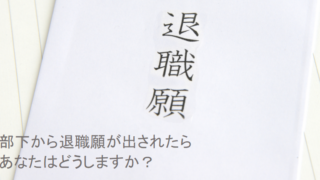
部下が退職を悩んでいる段階で声をかけるべき

このように、部下の退職を引き止めるためには、「その兆候を察知し、部下が退職を切り出す前にこちらから声をかけるべきである」とお伝えしました。
そして、最も効果的に退職を止めるための方法は、そもそも「退職を決断する」前に部下が仕事のことで悩んでいないかを把握することです。
これまでご紹介した兆候が出る前の段階で、
- 表情が暗い、元気がない
- 仕事のパフォーマンスが落ちている
- 連日機嫌が悪い
という様子があれば、何か悩みがあると疑うべきです。
こういう理由の場合、なんとなく「辞めたほうがいいかもしれない」と悩んでいるはいるものの、まで決断を下すまでには至っていません。
上司としてはこの状態のうちに悩みを聞き、適切な対応をとってやることが重要です。
一番いいのは、定期的に面談を行い、部下の悩みを吸い上げる機会をとることです。
その考え方や方法は、こちらの記事にまとめています。

サインを察知するのと同じくらい大切なこと
このように、部下の退職を防ぐためには、日ごろから部下の「負のサイン」を見逃さないことが大切です。
そして、それと同じくらい、上司が退職理由にならないことが大切です。
世の中の退職には、上司が原因であることがたくさんあります。
詳しくはこちらの記事にまとめています。
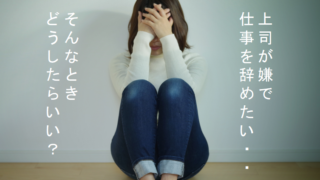
それに加えて、上司のふるまいによって回避できる退職リスクもあります。
部下の退職の兆候をつかむのと同じくらい、以下の退職リスクを生まないことも大切です。
「仕事内容が合わない」「給与が低い」という場合、上司個人の力量で何とかするのは難しいですが、以下の2点については、上司の動きによって退職リスクは少なくなります。
職場内の人間関係
職場で人間関係がこじれていないか気にかけ、何かトラブルがある場合は仲裁に務めなければなりません。
また、人間関係がこじれてしまう理由として、上司が部下に対して公平・公正に接しておらず、誰かをえこひいきすることがあります。
そのような点にも注意し、人間関係が原因で部下が退職を悩まぬようにしましょう。
休みが休めない(少ない)
上司が休日出勤を頻繁にしている場合は、メンバーに「自分も同じようにしなければいけないのか・・」という無言のプレッシャーがかかります。
また、そのスタンスに共感し、前向きな気持ちで休日出勤をする部下もいます。
このスタンスで仕事をする場合は、短期的には成果も上がりうまくいくこともありますが、長い目で見ると心身共に不健康になりやすく、退職してしまうというリスクがあります。
また、最近は働き方が変わっており、残業や休日出勤は極力避けるという考えが主流になっている点からも望ましくありません。
上司が休みをしっかりとるというスタンスを示すことで、メンバーもそれに習います。
突然「退職したい」と言われるのは上司失格
以上のような部下の退職の兆候を見つけることができれば、相手から退職を切り出される前に相談に乗ることができ、退職を引き止めやすくなります。
ハッキリと退職の意向を示された場合は、転職先を決めていたり決意が固まっていることが多く、そこから一生懸命説得しても上手くいかないことが多いものです。
退職を考えている部下には必ず表情や見た目、勤怠、仕事への姿勢に前兆が表れます。
その兆候を見つけることができず、部下から「辞めます」と切り出されて初めて気づくようでは上司失格と心得て、日々部下の様子を気にかけましょう。